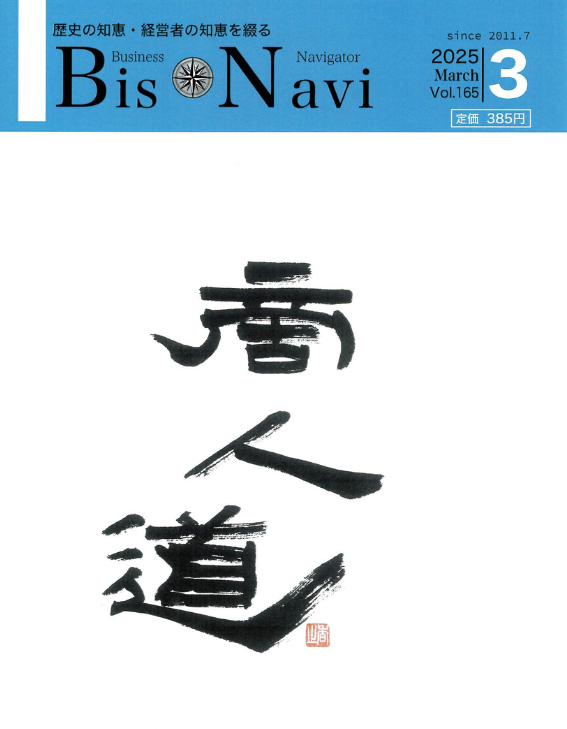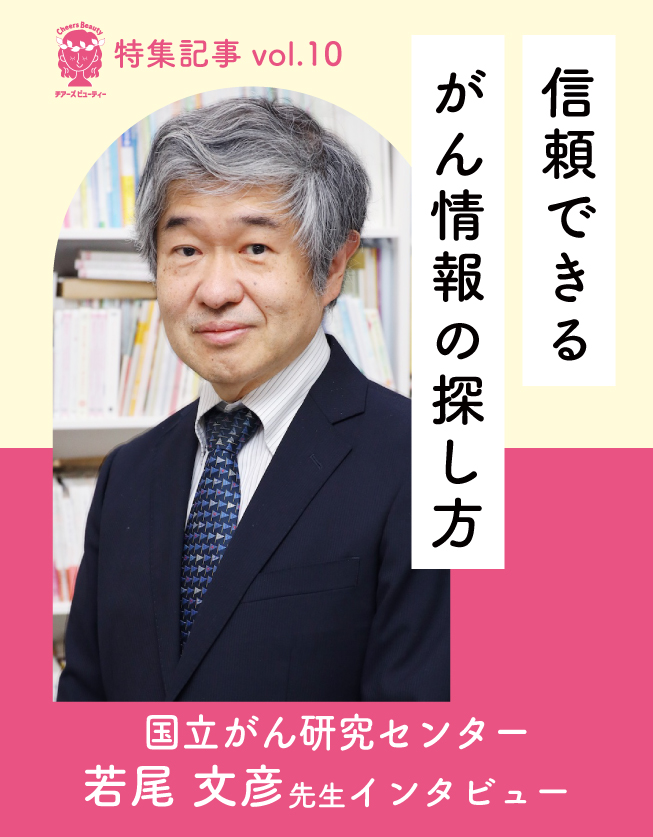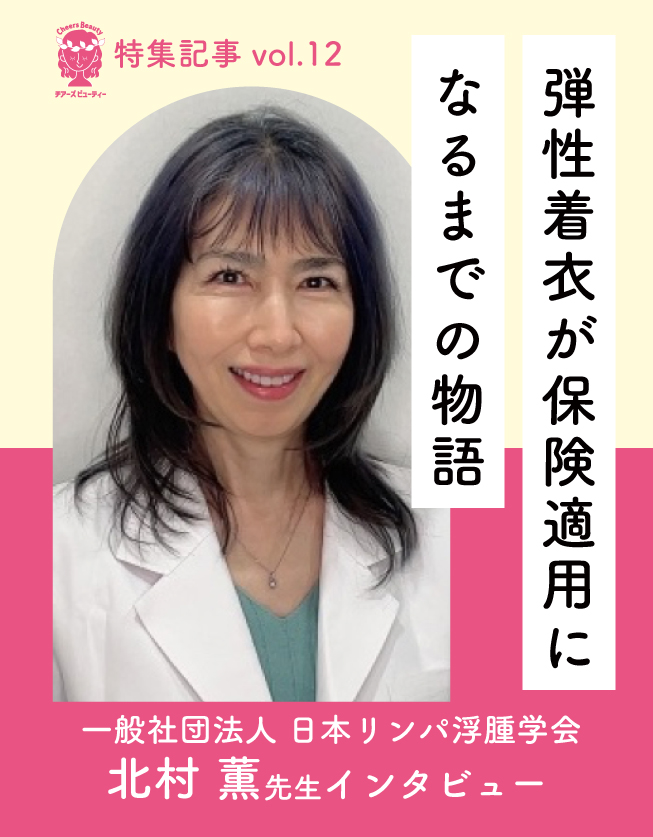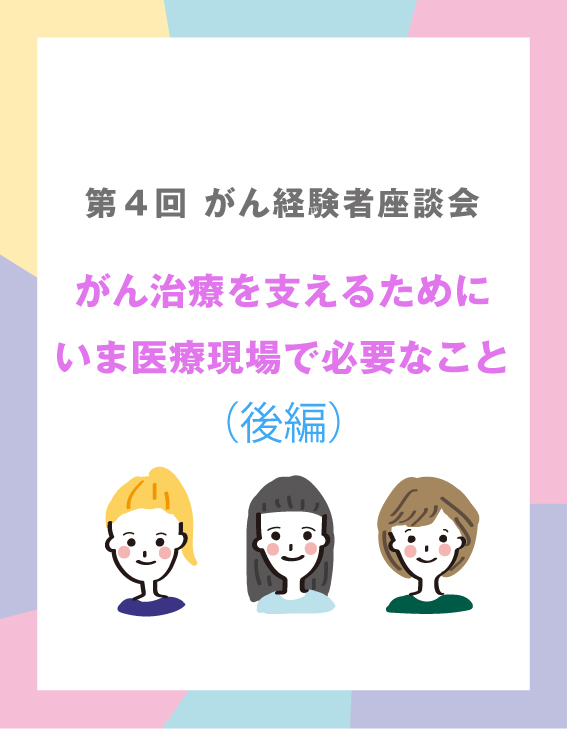私たちは日々、食事や生活習慣を大切にしながら、健康でいることを心がけています。
しかし、健康とはただ病気を予防するだけではなく、心身ともに充実した幸せな状態を指すものではないでしょうか。そんな考えを大切にしながら、食というアプローチから「統合食養学」という新しい栄養学をアメリカで学び、公認統合食養ヘルスコーチ (CINHC:Certified Integrative Nutrition Health Coach)として活躍する森 智世(もり ちせ)さんにお話を伺いました。
Profile

ソフィアウッズ・インスティテュート代表
公認統合食養/ホリスティックヘルスコーチ(CINHC)
公認国際ヘルスコーチ(CIHC)
森 智世(もり ちせ) さん
米国コロラド大学ボルダー校を卒業後、野村證券ドイツ法人を経て、米国ノートルダム大学経営大学院メンドーザ・カレッジ・オブ・ビジネスより企業財務・会計学専攻にて経営学修士号(MBA)を成績優等(Cum Laude)称号とともに取得。その後、野村證券をはじめ、数々の金融業界でディレクターとして、企業買収(M&A)や企業価値向上等に携わる。2010年、家族の健康問題から、20年以上携わってきた金融・投資銀行ビジネスを卒業。キャリアの大転換を図り、現在に至る。
▼バイオ個性で食べて健康と幸せを手にいれる統合食養学の情報サイト
ソフィアウッズ・インスティテュートの公式ブログ「図書室」
目次
医療や健康分野でのホリスティックなアプローチ
──森さんは、心と体をつなぎ、健康と幸せを手に入れるために、ホリスティックな食事法をコーチングされていると伺いました。ただ、日本では「ホリスティック」と聞くと、ちょっと怪しいものを連想する方も多いように思います
森:
そうですね。「ホリスティック」と聞くと、何となく怪しいとか、科学的ではないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。でも、それは「ホリスティック栄養学」という言葉に明確な定義が存在していないことによる部分が大きいと思います。
そもそも「ホリスティック」という言葉は、古代ギリシャ哲学のひとつの「ホーリズム」が由来です。これは、個々の要素を独立したものとして見るのではなく、全てはつながっていて、全体をひとつの完全体として見ることの大切さを表す考え方です。この考え方は、古代ギリシャの医療や健康分野に応用されてきた、とても奥深い哲学なんです。
──他の国では、ホリスティック哲学が医療にも取り入れられていると聞いたことがあります
森:
はい。アジアやヨーロッパではこのホリスティック哲学に基づいたアプローチが、代替医療の分野で広く取り入れられています。中国の中医学、インドのアーユルヴェーダ、欧州の自然療法やハーブ療法、さらには現代の予防医学や統合医療、機能性医療にも、「全体を見る」というホリスティックな視点が取り入れられています。
健康とは、食事や運動だけでなく、さまざまなライフスタイルや環境、心の状態も含めて成り立つもの。そうしたすべての要素を考慮していることが、ホリスティック・アプローチの本質なんです。
私がドイツに住んでいた頃の話ですが、向こうでは代替医療が浸透していて、例えば、インフルエンザにかかって病院に行くと、なんと薬ではなく、1週間の有給休暇が「処方」されるんです!会社は、このお休みを認めなくてはいけないんですよ。それも、通常の有給に加えてもらえる、お給料が100%保証された病欠なんです。インフルエンザは、薬よりも、しっかり休んで治しなさい、ということですね。
それから、虫刺されで手がパンパンに腫れた時も、病院へ行ったらハーブのティーバッグを処方されました。それを煮出して湿布するように、と。日本ではまず考えられませんね(笑)。ステロイドが処方されて終わりでしょう。でもドイツでは、「湿布なんてしていたら仕事になりませんよね」と、先生から3日間の有給休暇が追加で処方されたんです。手が腫れただけで!
 野村證券ドイツ法人勤務時代チームの食事会(1989-1992)(写真提供:森 智世さん)
野村證券ドイツ法人勤務時代チームの食事会(1989-1992)(写真提供:森 智世さん)
森:
ホリスティック哲学による「ホリスティック」の意味には、大きく二つあります。
1つは「私たちは、ひとり(個体)で存在しているのではなく、環境すべてと繋がった存在である」という意味。もう1つは、「ひとつひとつの部分を足し合わせても、全体ほどの価値はない」という意味です。
例えば、食べものなら、ビタミンA、C、Dを足し合わせたマルチビタミンを飲んだところで、リンゴまるまる1つを食べるほどの価値はないということを意味します。
──つまり、個々の部品を足し合わせても、1つの完全体は作れない、ということですね
森:
そのとおりです。この考え方は、ホリスティック医学と呼ばれる東洋医学では、「一物全体」や「身土不二」という言葉で表されています。
「統合食養学」も、このホリスティック哲学に基づいたアプローチです。
統合食養学では「ホールフード」そして「地産地消」「旬のものを食べる」という行動で表されます。食材をできるだけ自然のまま、丸ごと食べることで、栄養素同士の相乗効果や自然の生命エネルギーを無駄なくいただくこと、そして、生活している風土・環境・季節に沿った食事や生活をすることの大切さとして表されます。
ただ、日本では、従来の栄養学とは異なる怪しい食事法も「ホリスティック」という言葉を用いているケースがあります。そのため、「ホリスティック栄養学」と伝えると、誤解されてしまうのではないかと案じています。
「統合食養学」は科学的な裏付けのある情報に基づくエビデンスベースの栄養学です。また、例えば、アーユルヴェーダや東洋医学など、科学では証明がまだ追いついてないけれども過去からの実績が確認されている方法論からの知見も採り入れられています。
「統合食養学」とは?
心と体の両輪でウェルビーイングを実現
──「統合食養学」について教えてください
森:
「統合食養学」は、ジャシュア・ローゼンタール氏が40年ほど前にニューヨークで体系化した新しい栄養学です。英語では「 Integrative Nutrition」と言い、私はこれを「統合食養学」と訳して日本で紹介しています。
 72歳になるジャシュア・ローゼンタール氏のお誕生会にて(写真提供:森 智世さん)
72歳になるジャシュア・ローゼンタール氏のお誕生会にて(写真提供:森 智世さん)
「統合食養学」は、先ほどお話したホリスティック哲学の2つの理念に基づいています。
1つは、「私たちは環境、人間関係、仕事、ライフスタイルなど、あらゆるものとつながっている」という考え方。
実際、WHO(世界保健機関)も「ワンヘルス(One Health)」という概念を提唱し、「地球環境の健康と私たちの健康はつながっている」と発信しています。これはまさに、「統合食養学」の考え方そのものです。
もう1つは、「部分の総和よりも全体のほうが価値がある」という考え方です。この「全体」という考え方には、目に見えない心の存在も含まれます。私たちは肉体だけの存在ではなく、心や精神といった目に見えない要素をもった1人の人間として存在しています。
例えば、どんなに栄養バランスのとれた食事をしていても、ストレスや心に不調があれば、健康とは言えません。だからこそ、心にも栄養を与えることが大切なんです。
これについてもWHO(世界保健機関)は、健康の定義として「身体的・精神的・社会的に完全に健全な状態」と、3つの要素を含めています。「統合食養学」は、これら3つを組み入れた新しい栄養学なんです。
──それは、まさにウェルビーイングの考え方ですね!
森:
そうですね。最近、日本でも「ウェルビーイング」という言葉が広まってきましたが、「統合食養学」はまさにその実現を目指しています。
「統合食養学」では、口にする食べ物を「セカンダリーフード」、心に栄養を与えるものを「プライマリーフード」と呼びます。
心が満たされていないと、お腹が空いていないのにジャンクフードに手を伸ばしてしまったり、健康的な習慣が続けにくくなります。だからこそ、まずは心を栄養で満たすことが大切なんです。
心の栄養が最も大切だから、「プライマリーフード」なんです。単に食事のコーチングをするのではなく、「その人が本当に求めている心の栄養は何か?」を一緒に考え、寄り沿って伴走することが私たちヘルスコーチの役割です。
バリキャリからヘルスコーチへ
──森さんが「統合食養学」に出会ったきっかけを教えていただけますか?
森:
当時、私は金融業界でM&Aのディレクターとして、寝る間もなく忙しく働いていました。そんな中で、家族が病気になってしまったんです。
思い悩んでいた時、イギリス人の上司の言葉が私の背中を押してくれ、思い切って仕事を辞める決断をしました。
 経営コンサルタント時代のプロジェクトチーム(写真提供:森 智世さん)
経営コンサルタント時代のプロジェクトチーム(写真提供:森 智世さん)
私はそれまで食事も料理も疎かにしていて、空腹を満たせれば何でもいい、料理は時間の無駄とさえ思っていましたから、家族のケアをするための知識は全くありませんでした。
でも、長年の職業病でしょうか。証券会社でリサーチ畑を歩んできた私は、どんな情報も裏付けがないとなかなか信用できません。最低3つの裏付けがないと信用できない。巷に溢れる健康情報をにわかに信用する気持ちにはなれず、そこで、「きちんと裏付けされた知識を学ぶなら、やっぱり学校だ!」と思い立ち、女子栄養大学の通信教育課程に入学することにしたのです。
女子栄養大学は、管理栄養士さんなら必ず学ぶ四群点数法を開発された香川綾先生が設立された学校です。厚生労働省の活動や文部科学省が公表している食品成分表の作成にも携わっている先生方から学ぶことができ、栄養学の基礎をしっかりと学ぶことができました。
そんなある日、以前の会社の上司から「HAPPINESS ADVANTAGE(邦題:幸福優位7つの法則)」という本を勧めらました。ハーバード大学のポジティブ心理学の教授、ショーン・エイカー博士が書かれた本でした。

いつもの私はあまり啓発本に興味がないのですが、尊敬する元上司からのお勧めでしたので読んでみることにしたのです。するとそこには、心が沈んだ時に自分の中の幸福感を高める方法が書かれていました。半信半疑で試してみたところ、わずか1週間で気持ちが上向いていったんです。
自分の心の変化に驚き、「こんなに効果があるなんて!」と感動し、すぐにSNSで本の感想をシェアしました。その時、女子栄養大学で栄養学を学び始めたことも併せて報告しました。
すると、MBA時代のアメリカ人のクラスメートから、「その2つを融合した新しい栄養学が学べる学校がニューヨークにあるよ」とコメントをもらったんです。それが「統合食養学」との出会いでした。
調べることが大好きな私が詳しい情報も確認せず、勢いで入学ボタンをクリックしていました(笑)。もちろん、彼女が信頼できる友人だったということもありますが、何よりも、ポジティブ心理学と栄養学を組み合わせた学問という点に、直感的に「これだ!」と思ったんです。
入学してみると、先生方の顔ぶれも豪華でした。
機能性医療や予防医療、統合医療の専門家である医師が多数在籍し、中には統合医療の第一人者であるアンドリュー・ワイル先生や、ハーバード大学公衆衛生大学院教授でもあり栄養疫学研究の第一人者であるウォルター・ウィレット先生、アーユルヴェーダの権威であるディーパック・チョプラ先生といった著名人も名を連ねていました。
まさに、ドリームチームと呼べる、素晴らしい先生方から学ぶことができたんです。
家族の健康のために学び始めたので、当初、ヘルスコーチとして活動することは考えていませんでした。しかし、この学校では、起業に必要な諸々を教える授業もあり、そこで出された課題、例えば、ホームページを作りましょうとか、ドメインを取得しましょうといった課題を、宿題として実行していったら、いつの間にか、課題で造っただけのホームページからヘルスコーチングのご依頼が入るようになったのです。
そこで、わたしが学んだ知識やスキルが家族以外の人たちにとっても役に立つのであればと、ご依頼を受けたことがヘルスコーチとしての一歩となりました。
 米国ノートルダム大学経営大学院メンドーザ・カレッジ・オブ・ビジネスより企業財務・会計学専攻にて経営学修士号(MBA)を成績優等(Cum Laude)称号とともに取得。MBA卒業式30代(1995)(写真提供:森 智世さん)
米国ノートルダム大学経営大学院メンドーザ・カレッジ・オブ・ビジネスより企業財務・会計学専攻にて経営学修士号(MBA)を成績優等(Cum Laude)称号とともに取得。MBA卒業式30代(1995)(写真提供:森 智世さん)
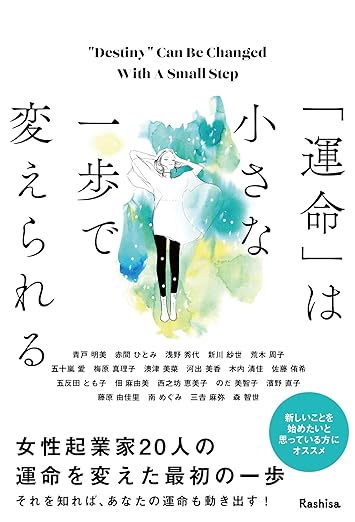
森さんがヘルスコーチになったいきさつなどについて綴っている書籍
2024.3.19 発売
ウェルビーイングを目指す、ヘルスコーチの役割
──「公認統合食養ヘルスコーチ」とはどのような活動をされるのですか?
森:
「統合食養学」のアプローチに基づいて、6ヶ月間、二人三脚で伴走していきます。その人が達成したい目標を最初に決めて、それに向かって、食事だけでなく、生活全般に関わることへのコーチングをしながら、その人が自分らしく健康でいられる方法を見つけていきます。
 コーチングの様子。体の不調でご相談に来られ、プログラム修了時には、心の状態が大きく改善したことを実感できる(写真提供:森 智世さん)
コーチングの様子。体の不調でご相談に来られ、プログラム修了時には、心の状態が大きく改善したことを実感できる(写真提供:森 智世さん)
──森さんのコーチングは、「これはダメ」と制限するのではなく、代わりになるものを提案してくれるのが素晴らしいなと感じます
森:
ありがとうございます。統合食養学には「クラウディング・アウト」という考え方があって、悪いものを避けるのではなく、良いものを増やすことで、自然と悪いものが入り込む余地を少なくするというアプローチです。
ダメと言われるほど食べたくなるのが人間ですからね(笑)
もちろん、不調や病気によっては、食べて欲しくないものもあります。そういう時には、「これは控えたほうがいいけど、代わりにこんなものがあるよ」と、代替できる食品の紹介もします。例えば「生クリームは食べて欲しくないけど、生クリームのようなものをカシューミルクで作れるんですよ」とお伝えしています。
もちろん手間がかかるものもありますが、工夫次第で生活の質を落とさなくても良いことが多いんです。「こんな食品があるんだ!」という新しい出会いにもなります。それに、私がヘルスコーチになった10年前は、何でも手作りしないといけなかったんですが、今はネットで探せば、いろいろなものが手に入る時代になりました。
乳製品を使わないバースデーケーキや、小麦粉・白砂糖不使用のお菓子など、選択肢が増えて、本当に便利になりましたよね。
──単に自分ひとりが健康でいることではなく、家庭や仕事、心と体の健康を含めた「統合的な幸せ」、つまりウェルビーイングを目指していくことが最終的な目的なのでしょうか?
森:
そうですね。健康は本人だけの問題ではなく、家族の影響も大きいですよね。だからヘルスコーチングの中では、家族についての相談もよく受けます。「息子がこういう食生活をしていて心配」「娘がPMSがひどくて、いつも薬を飲んでいる」といったお話を伺うこともあります。
そういうときは、「それなら、こんな食材を取り入れてみたらどうでしょう?」と、ご家族の健康も含めたコーチングもします。
クライアントさん自身のウェルビーイングを高めるためには、家族の健康や幸せも大事な要素。だからこそ、統合食養学のヘルスコーチングは、クライアントさんを取り巻くさまざまなことも一緒に考えながら進めていくんです。「あなたは環境全てとつながっている」からです。
──お話を伺っていて、心の安定は食でも作られるし、その食を通じた人間関係が心の栄養にもなっているのかなと感じます
統合食養学で自分らしい健康と幸せを
森:
1対1のコーチングだけでなく、「統合食養学」を日本語で学べる講座も開いているんですよ。12のテーマに沿って学んでいくのですが、その中には、「女性ホルモンと仲良くなる方法」などのレクチャーもあります。
 講座の様子。情報の確かさと分かりやすさが好評(写真提供:森 智世さん)
講座の様子。情報の確かさと分かりやすさが好評(写真提供:森 智世さん)
生理周期ごとの過ごし方や、どんなものを食べると良いか、症状に応じた対策、ライフスタイルの工夫などをお伝えしています。
例えば、排卵後の生理前の高温期になると、だんだん体が重くなって、感情がネガティブに傾きやすかったり、PMSの症状がつらくなる時がありますよね。そんなときは、無理せず「いっそ、おうちに引きこもりましょう」とお伝えしています(笑)。
今は在宅勤務ができる環境の方も増えていますし、この時期は意識的に外に出るのを控えるのもひとつの方法です。生理前は普段なら気にならないようなことが心に引っかかったり、ちょっとしたことでイライラしてしまったりすることもあるので、自分のためにも、周りのためにも、できるだけ穏やかでいられる環境で過ごすことが大切です。
また、大事な会議やプレゼンなどは、生理周期のどのタイミングで行うのがベストか、といったこともお伝えしています。自分のリズムを知り、上手に付き合うことで、日々のパフォーマンスも変わってくるんです。
 ホリスティック・アプローチによるウェルビーイング経営導入に関心のある企業にセミナーを行っている森さん(写真:ソフィアウッズ・インスティテュート公式サイトより)
ホリスティック・アプローチによるウェルビーイング経営導入に関心のある企業にセミナーを行っている森さん(写真:ソフィアウッズ・インスティテュート公式サイトより)
──本当にそう思います。自分で自分をコントロールするというか、自分のモチベーションスイッチをどう押すか、自分のトリセツが分からないと、パフォーマンスに繋がらないですよね
森:
そうですね。体の声を聞くことはすごく大切。「統合食養学」を作ったジャシュア・ローゼンタール先生も、繰り返し、『頭の声ではなく、体の声を聴きなさい』とおしゃっていました。
健康情報が溢れている今の環境で、わたしたちは多くの情報を知っていますが、そうすると、”この症状はこれが原因に違いない”とか、”これを食べなきゃいけない”というように、ついどこからか聞いたルールに当てはめて考えようとしてしまいます。でも、外から与えられた情報ではなく、まず、自分の体に聞いてみることが大事なんです。
なぜなら、あなたの “バイオ個性” は、世界にたった一つしかないからです。
たとえば、誰かに効果のあった方法が、あなたにも効果があるとは限りません。だからこそ、あなたの体が何に「イエス」と言い、何に「ノー」と言っているのかを、ちゃんと感じ取ることが大切なんです。
でも実際には、自分の体の声に耳を傾ける習慣がない人が、本当に多いと感じます。与えられた情報をそのまま信じてしまって、「ブロッコリーがいい」と聞けばスーパーからブロッコリーが消えたり、「小麦粉が悪い」と聞けば、みんなが一斉にグルテンフリーに走ったり…。でも、ちょっと立ち止まって考えてみてほしいんです。
『今まで20年、30年生きてきて、食パンを食べて何か問題がありましたか?』って。特に何もなかったのに、なぜ今、無理に抜こうとするんでしょう? もちろん、「もしかしてこれが原因かも?」と感じることがあるなら、試しにやめてみるのはいいと思います。でも、特に、今まで病気になることもなく、おいしく給食を食べてきたのなら、今更制限する必要はないですよね。
私たちは、情報に振り回されがちです。でも本当に大切なのは、自分の体と対話すること。その上で、自分に合った選択をしていくことが大事なんじゃないかと思います。
──「”バイオ個性”とは、遺伝子のように一人ひとり異なるものなのでしょうか?
森:
はい、実は遺伝子以上に違います。遺伝子というと、一卵性双生児は同じ遺伝子を持っていますよね。でも、「統合食養学」では、一卵性双生児も異なる”バイオ個性”を持っていると考えます。
“バイオ個性”は、2つの要素から成り立っています。1つは「コンスティテューション(constitution)」、もうひとつは「コンディション(condition)」です。
コンスティテューションというのは、自分の努力ではもう変えられない部分です。ここには、遺伝的なことも血液型なども含まれます。それ以外にも、例えばお母さんのお腹の中にいた時の栄養状態だったり、生まれた後の生育環境などが含まれます。まだ自分の意思で食事やライフスタイルを選べなかった時の、親や保護者の管理下でどのように過ごしてきたかが、コンスティテューションとなります。
コンディションは、自分の努力で変えられるものです。たとえば、生活習慣や食事、運動、人間関係や仕事など、努力すればこれからでも変えることができるものがコンディションです。
例えば、コンスティテューションが糖尿病になりやすかったり、太りやすかったとしても、そのコンスティテューションに合わせて、コンディションを変えていくことで、そのリスクを顕在化させずに済む可能性が高くなります。
がんも90%はライフスタイル要因です。適切なライフスタイルを送ることで予防が可能です。コンスティテューションとコンディションを理解し、コンスティテューションに沿ってコンディションを整えることで、がんになりにくくすることができるんです。
また、一卵性双生児の話に戻りますが、確かに彼らのコンスティテューションは同じかもしれません。でも、大人になってからは、同じ人と結婚することもなければ、同じ職場で働くこともないですよね。つまり、人間関係や住んでいる環境も違います。私たちは環境全体とつながっている存在なので、それぞれの “バイオ個性” は絶対に異なるんです。
だから、「統合食養学」では、その人のバイオ個性に合ったアプローチをするという考え方を大切にしています。もし同じ不調を持つクライアントさんが2人いたとしても、ヘルスコーチングのプログラムの内容が同じになることはありません。ひとりひとりのバイオ個性に沿ったアプローチが大切なんです。
「統合食養学」は、日本では、まだ新しい分野ですが、健康と幸せを追求する皆さんにとって、大きな可能性を秘めていると信じています。これからも、より多くの方に「統合食養学」を知っていただき、健康で幸せな人生を送るための手助けができれば嬉しいです。
インタビューを終えて・・・
もちろん、病気になったときは医療の力を借りることも大切。でも、そもそも病気にならないために、生活や食事、運動など、自分の周りにあるものをもっと深く知って、自由に選べるようになってもいいんじゃないかと思いました。
森さんは、ライフスタイルの改善や自分に合った食事などについて、あなたを取り巻く様々なこと(環境、仕事、家族、人間関係など)を考慮したコーチングを提供されています。
ご興味のある方はサイトをチエックしてみてください♪
ソフィアウッズ・インスティテュート公式サイト
【インタビュー記事担当者】
編集長:上田あい子
編集ライター:友永真麗